![]()
![]()
音波は,物理的には媒質(空気)の粒子の振動およびそれにともなって生じる圧力の変動か媒質中を伝搬していく現象といえる。
音場(音波の伝搬している空間)内の各点では,圧力の高い密部と圧力の低い疎部が交互にやってきて,大気圧を中心として微小な圧力の上昇下降を繰り返す。この圧力の変化分を「音圧」といい,1秒間のこの圧力変動の数を周波数とよぶ(単位「Hz」でヘルツと呼ぶ)。
我々が聴くことのできる音のエネルギーはごく微弱ではある,その範囲は最大と最小の比が1012に及んで非常に広い。それで,そのままの値で扱うと取扱いが不便なので,適当な基準の量に対する比をとり,その対数をとった相対的な量表示を行うことが多い。
表すべき音の強さをI,音圧をPとしたとき,基準となる音の強さをI0,その音圧をP0とすると,
| ……(1) | |
| ……(2) |
強さを式(1)で表したものを音の強さのレベル,音圧を式(2)で表したものを音圧レベルといい,単位は,dB(デシベル)である。
これらはあくまで相対的な大きさを表しているので必ず基準の量を明示しなければならないが,一般に空気中では,
I0 = 10-12W/m2, P0 = 20μPa
但し, W = ワット
Pa = パスカル
= kgf/m2
で表わすことになっており,この場合には基準を明示しないことがある。これらの基準の値はいずれも最近まで,1000Hzの基準的な最小可聴限とされていた音の強さおよび音圧に相当する値なのである。一般に,音の強さを直接測定することは困難であり,音圧レベルによって音の強弱を比較するのがふつうである。図1-1に音圧レベルの目安を示す。
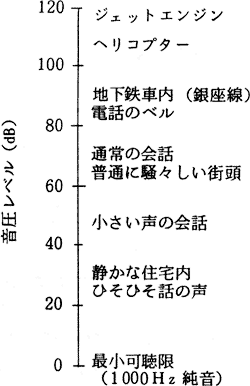 |
|
図1-1 音圧レベルの目安 |
デジベル値は次のような性質をもつ。エネルギーが2倍になる毎にレベルは3dB上昇する。すなわち,4倍では6dB,8倍では9dBの上昇となる。また,10倍になる毎に10dBの上昇であり,100倍で20dB,1000倍で30dBの上昇となる。例えば,80dBの騒音源が2つあれば83 dBの騒音となり,10個あれば90dBの騒音となる。