![]()
|
図2-1 等ラウドネスレベル曲線 |
一般にはヒトの可聴周波数は20Hz〜20000Hzと言われているが、20Hz以下の周波数になると、とたんに聴こえなくなるというわけではなく、低い周波数ほど耳の感度が悪くなり、高い音圧レベルでないと聴きとることができないという関係にある。グラフ1-2の最小可聴値として示された破線を見ると、20Hzでの最小可聴音の音圧レベルは70dBにも達しており、通常存在する程度の音圧での可聴周波数の下限を便宜的に20Hzとしたものと思われる。
20Hz以下の周波数の音の最小可聴音圧レベルについても多くの人により研究がなされ、「1Hzというような非常に低い周波数の音であっても、その大きさの度合い、すなわちラウドネスをききわけることができる」と言われている。図2-2に超低周波音域での可聴閾値の実験結果が示されている。
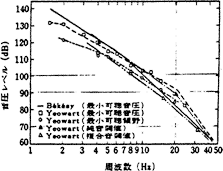
図2-2 超低周波音域の可聴闇値 |
可聴閾値に個人差が大きいことはわが国での最近の研究により明らかになってきた。
図2-3には岡井らによる実験の結果を示す。その図中、A,Bと示されている2本の曲線は低周波音による被害を長年にわたって受けてきた人の最小可聴値である。他の人々よりも著しく低い値となっていることがわかる。山田も最小可聴値の実験をおこなっている。その結果を図2-4に示すが、最も感度の良い人と最も悪い人では20〜25dB程度の差があることが明らかである。
閾値は、実験条件によっても値が大きく異なることも示されている。山田は上の実験では、低周波音発生用のスピーカのエッジから出る可聴音のノイズを低く抑えることにより、最小可聴値の平均値で、これまでの研究よりも10dB程度低い値を得ている。図2-4には岡井らによる最小可聴値平均値も示されているが、山田の結果よりも10dB程度高くなっている。
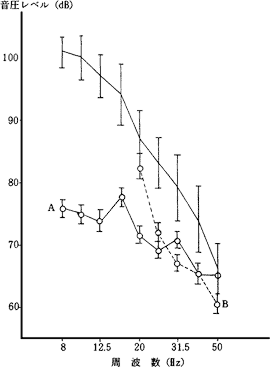
グラフ2-3 低周波音の閾値 |
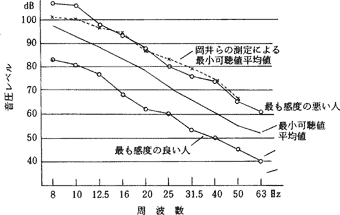
グラフ2-4 最小可聴値 |
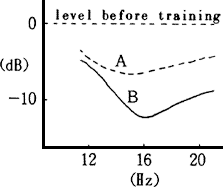
図2-5 訓練による閾値低下 |
最小可聴値は「訓練」によって低下することが斉藤により示されている。図2-5は、「通常の感度を持つ健常者を、16Hzに対する感覚が生じるように訓練した結果、閾値が低下した例」である。低周波音に日々さらされている人はこの訓練効果により一般の人よりも閾値が低下している可能性がある。汐見は数年経ってやっと妻の訴える低周波音の被害が分かるようになった男性の例を報告している。
上に述べたように、閾値には個人差が非常に大きいこと、実験条件によっても大きく異なること、「訓練効果」により閾値が下がることなどから、低周波音の閾値(最小可聴値)を一般的に決定することには無理があると思われる。
次に、可聴閾値とは少し異なるが、山田はストレスとなる最小のレベルとして、「3分間の暴露により少しでも気分の悪くなるレベル」を実験により求めた。彼はこれをアノイアンス(わずらわしく迷惑であること)の閥値と呼んでいる。これを平均の最小可聴値とともに示したのが図2-6である。最小可聴値およびアノイアンスの閥値の両者とも周波数が低くなるほどレベルは高くなるが、両者の差は小さくなる傾向がある。このことを明確にするため、各被験者のアノイアンスの閥値と最小可聴値との差をとったものが図2-7に示されている。この差は、各被験者が自分の最小可聴値よりも何dB高い値で気分が悪くなったのかを示している。低い周波数ほどこの差が小さく、この実験での最低周波数8Hzでは両者にほとんど差がないことがわかる。すなわち、低い周波数では感知しはじめるレベルではすでに不快感をともなっている場合が多いことを示している。また、この実験では暴露時間は3分間にすぎないが、さらに長い暴露時間の実験をおこなえば、このアノイアンスの閥値はより低くなると考えるのは妥当であろう。衛生工学ハンドブックは次のことを指摘している。「12〜15Hzの超低周波音の80dB前後の暴露を中断した際に、身体的症状の有無にかかわらず、また、たとえ難聴者であっても、この暴露の中断を快く感じていることが、Leiberによって明らかにされている。このことは、超低周波音の暴露による不快さが、具体的に生理的影響などの形で表現できない状態のものであっても、少なくとも暴露のないときに比べて不快であることを間接的に示すものである」。12〜15Hz,80dB前後の低周波音というのは、図2-2によれば最小可聴値以下である。
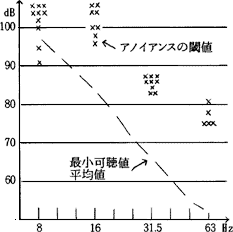
図2-6 アノイアンスの閾値 |
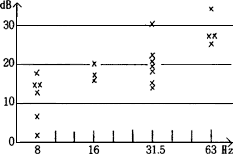
図2-7 アノイアンスの閾値と各個人の最小可聴値との差 |
以上、低周波音の閥値(最小可聴値)には可聴音の場合とは異なった様々な問題があることを述べた。低周波音は、最小可聴音圧レベル以下でも何らかの生理的影響を生じる可能性がある。