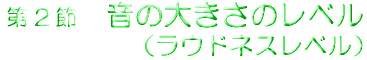
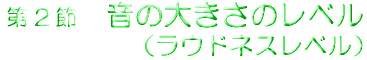
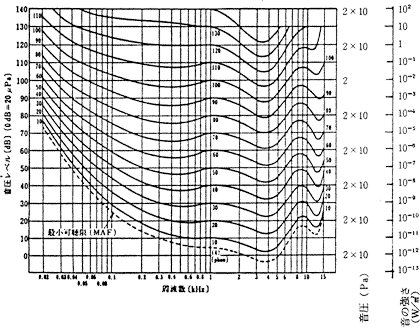 |
|
図1-2 純音の音の大きさの等感曲線 |
耳の感度は周波数によって異なり,同じ音圧の音もその周波数が異なると大きさが違って感ぜられる。ある音の大きさを,これと同じ大きさに聞こえる1000Hz純音の音圧のレベル(dB)の数値で表わして,ラウドネスレベルあるいは大きさのレベルといい,単位にはphonを用いる。例えば,音圧レベル90dBの40Hz純音のラウドネスレベルは図1-2より70phonであることがわかる。各種の純音の周波数と音圧レベルに対して等しいラウドネスレベルになる点を結べば,図1-2となり,これを等ラウドネスレベル曲線とよんでいる。この図はイギリスの国立物理学研究所における大規模な実験の結果で,1000Hzの平均的な最小可聴限が,それまで長い間音の大きさのレベルの基準となっていたフレッチャーの測定よりも4dB高くなったので,最小可聴限が0phonでなくて4phonとなっている。
図から明らかなように,低音では1000Hzの音に比較して高い音圧レベルでないと等しい大きさに聴こえない。また,ここで注意すべき点は,ラウドネスレベルが大きいほど曲線が平担に近くなっていること(注1)と,低音部では曲線がつまっていて(注2),小さい音ほど傾斜が急になっていることである。
(注1)大きい音の場合と小さい音の場合とでは耳の周波数特性は異なっている。
具体例としては,レコードを小さな音で聞いた場合,低音が不足しているように聞こえる。
(注2)音圧レベルを低いところからしだいに上げていった場合,周波数の低い音はなかなか聞こえるようにならないが,聞こえ始めてからの音の大きさの増大が急激であることを意味する。例えば,音圧レベルが80dBから90dBへ10dB上昇すると,20Hzでは,約20phonの上昇を示しており,1000Hzと比較して約2倍の増大である。