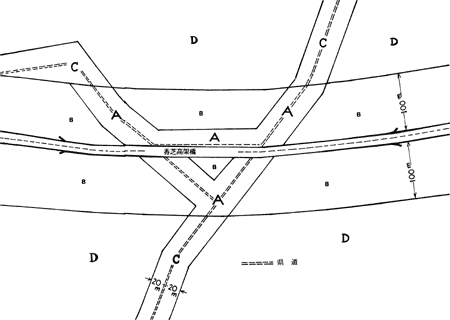 |
|
図4-7 A~D地域の範囲 |
3-3 香芝高架橋と旧県道の両方を考慮した建物被害の分析
前節までの建物被害の分析によって,①香芝高架橋との関係では,約100mの範囲内で建物の被害が多いこと,②旧県道との関係では,旧県道に接している建物の被害は多いが,旧県道から建物1棟分ぐらいの距離(約10~30m)離れると。被害は少なくなる-ことがわかった。
以上の二点が正しければ,香芝高架橋と旧県道の両方に近い地域の建物被害の発生率と両方から遠い地域の建物被害の発生率は,大きな差が出るはずである。この仮説を検証するために,まず,次のように,地域を四つに分割する。
この地域割りを図示したものが,図4-7であるが,A地域は,香芝高架橋からも旧県道からも近く,両方の被害をうけるおそれのある地域である。B地域とC地域は,どちらか一方の被害をうけるおそれのある地域である。D地域は,両者から離れており,被害が少ないと推定される地域である。
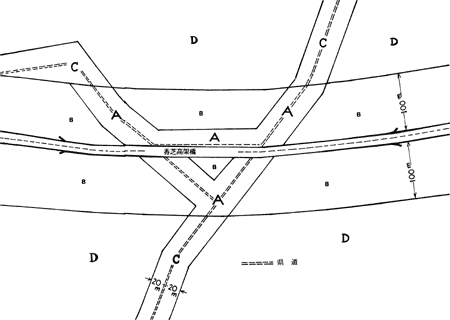 |
|
図4-7 A~D地域の範囲 |
(注)旧県道との関係で20mとしたが,これは住宅地図によれば,建物の敷地の奥行きが,10~25mになるからにすぎず,おおよその目安にすぎない。つまり,旧県道の影響範囲は20mであると断定しているわけではない。その意味では,香芝高架橋の影響範囲も,100mであると断定しているわけではなく,おおよその 目安にすぎない。
3-3-1 壁のひび割れと建物のゆがみ
「外壁のひび割れ」,「屋内の壁のひび割れ」,「風場の壁のタイルのひび割れ」の被害のうち,どれかひとつでも。「ひどいひび割れ」又は「少しひび割れ」がある建物と,全く無い建物に分け,それらの分布を地図上に示すと,図4-8のようになる。
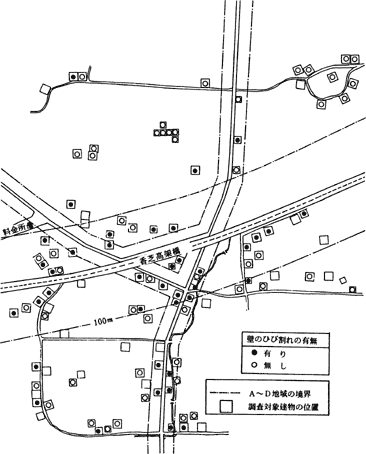 |
|
図4-8 壁のひび割れのある建物の分布 |
表4-8 壁のひび割れ
| 地域 | 壁のひび割れ | ひび割れのある建物の割合
①/(①+②) (%) |
||
| ① あり | ② なし | ③ 不明 | ||
| A | 9 | 2 | 1 | 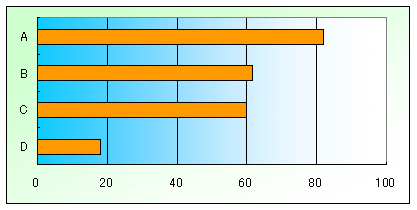 |
| B | 16 | 10 | 4 | |
| C | 6 | 4 | 1 | |
| D | 8 | 35 | 15 | |
この図上で,前述のA,B,C,Dの4地域について,建物被害の発生率を求めると,表4-8に示すように,香芝高架橋と旧県道の両方に近いA地域と両者から遠いD地域では,被害に格段の差があることがわかる。
| 地域 | 壁のひび割れ | ひび割れのある建物の割合
①/(①+②) (%) |
||
| ① あり | ② なし | ③ 不明 | ||
| A | 7 | 5 | 0 | 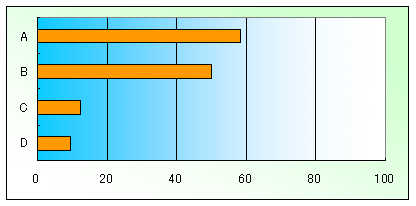 |
| B | 12 | 12 | 6 | |
| C | 1 | 7 | 3 | |
| D | 4 | 38 | 16 | |
次に、建物のゆがみについても,同様にすると(図は省く),表4-9のようになり,ここでもA地域とD地域では被害に格段の差があることがわかる。
3-3-2 建物の新旧との関係の考慮
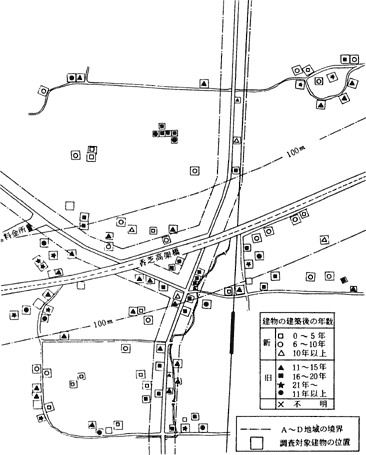 |
|
図4-9 建物の建築後の年数の分布 |
A~D地域について,建物の新旧の分布を地図上にプロットし(図4-9),この図から地域ごとに,建築後11年以上を経た建物の割合を求めると,表4-10のようになる。
表4-10 建物の新旧 |
|||||||||||||||||||||||||
この表から,D地域の建物は,A,B,C地域に比べて,古い建物が少ないが,その差は,わずかであることがわかる。
従って,前述のA地域とD地域の建物被害の格段の差は,建物の老朽化による影響は,わずかであり,道路に近いか否かが主な要因であると言えよう。